EBMとその応用について
Evidence-Based Medicine(EBM)とは、『実地医療の場において、患者個々の病態、環境や価値観を勘案して、科学的な根拠(エビデンス)に基づいた、その患者にとって最適な医療を提供するための意思決定をすること』 と理解されている。そのプロセスとしては、まずは日常診療での疑問点を明らかにし、次いでそれに関する情報を収集・吟味し、個々の患者への妥当性を正しく評価した上で、意思決定をする過程が想定される(図1)。このようなEBMの基本姿勢は、医療を画一化するものではなく、あくまでも個別性を最大限に尊重するものである。
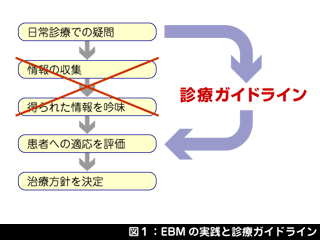
EBMの実践に際しては、日常の診療に多忙な医療者が必要な情報を迅速に取得し、かつ正しく吟味し、適用することは容易ではない。診療ガイドラインは、その時点での最良の医療を効果的かつ効率的に提供すること、“すなわちEBMの実践を支援するもの”である(図1)。加えて、患者を中心としたチーム医療における情報共有のツール(手引き)としても診療ガイドラインは不可欠である。
診療ガイドラインは、『特定の臨床状況のもとで、適切な医療について判断が下せるように支援する目的で、体系的に作成された文書(Field MJら)』 であり、利用に際しては個々の医療機関の状況、患者の価値観や社会規範を考慮してあくまでも柔軟に使いこなす必要がある。一般的な理解として、『診療ガイドラインとはせいぜい60〜95%の患者に適応されるもの(Eddy DM)』 と理解されている。したがって、医師個人の裁量権を規制するものではなく、かつ医事紛争や医療訴訟の資料さらには保険診療の審査基準などに使用されることのないようにしなければならない。しかし、診療ガイドラインが存在することで、医療行為についての判断根拠(説明責任)が問われることも認識しておく必要がある。
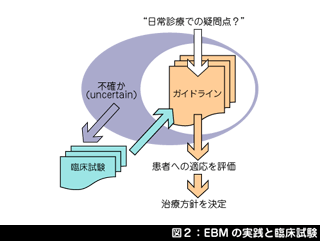
EBMの実践ツールとしての診療ガイドラインでは、定期的(一般的には2〜3年が目途)に評価・更新するとともに、その最終アウトカムとしての医療の質向上が問われている。反面、診療ガイドラインがカバーできる範囲は限られており、新たな疑問点や不確か(uncertain)なことについては、質の高い臨床試験の計画や、それらへの積極的な参加(エビデンスを作る)が望まれている(図2)。
(高塚雄一)