1.がん疼痛の分類・機序・症候群
国際疼痛学会は「痛み」を「実際に何らかの組織損傷が起こった時,あるいは組織損傷が起こりそうな時,あるいはそのような損傷の際に表現されるような,不快な感覚体験および情動体験」と定義している。痛みは主観的な症状であり,心理社会的,スピリチュアルな要素の修飾を受ける。痛みの神経学的機序(性質の分類),パターン,原因(疼痛症候群)の診断を的確に行い,診断結果に従って速やかに適切な薬物療法および原因治療を行うことが重要である。
1.痛みの性質による分類
痛みの神経学的分類を表1 に示す。
| 分 類 | 侵害受容性疼痛 | 神経障害性疼痛 | |
|---|---|---|---|
| 体性痛 | 内臓痛 | ||
障害部位 |
皮膚,骨,関節,筋肉,結合組織などの体性組織 | 食道,胃,小腸,大腸などの管腔臓器肝臓,腎臓などの被膜をもつ固形臓器 | 末梢神経,脊髄神経,視床,大脳などの痛みの伝達路 |
痛みを起こす刺激 |
切る,刺す,叩くなどの機械的刺激 | 管腔臓器の内圧上昇臓器被膜の急激な伸展臓器局所および周囲組織の炎症 | 神経の圧迫,断裂 |
例 |
骨転移局所の痛み術後早期の創部痛筋膜や骨格筋の炎症に伴う痛み | 消化管閉塞に伴う腹痛肝臓腫瘍内出血に伴う上腹部,側腹部痛膵臓がんに伴う上腹部,背部痛 | がんの腕神経叢浸潤に伴う上肢のしびれ感を伴う痛み脊椎転移の硬膜外浸潤,脊髄圧迫症候群に伴う背部痛化学療法後の手・足の痛み |
痛みの特徴 |
局在が明瞭な持続痛が体動に伴って増悪する | 深く絞られるような,押されるような痛み局在が不明瞭 | 障害神経支配領域のしびれ感を伴う痛み電気が走るような痛み |
随伴症状 |
頭蓋骨,脊椎転移では病巣から離れた場所に特徴的な関連痛*を認める | 悪心・嘔吐,発汗などを伴うことがある病巣から離れた場所に関連痛を認める | 知覚低下,知覚異常,運動障害を伴う |
治療における特徴 |
突出痛に対するレスキュー薬<の使用が重要 | オピオイドが有効なことが多い | 難治性で鎮痛補助薬が必要になることが多い |
*:関連痛
病巣の周囲や病巣から離れた場所に発生する痛みを関連痛と呼ぶ。内臓のがんにおいても病巣から離れた部位に関連痛が発生する。内臓が痛み刺激を入力する脊髄レベルに同様に痛み刺激を入力する皮膚の痛覚過敏,同じ脊髄レベルに遠心路核をもつ筋肉の収縮に伴う圧痛,交感神経の興奮に伴う皮膚血流の低下や立毛筋の収縮を認める。上腹部内臓のがんで肩や背中が痛くなること,腎・尿路の異常で鼠径部が痛くなること,骨盤内の腫瘍に伴って腰痛や会陰部の痛みが出現することなどが挙げられる。
(参考)椎体症候群
骨転移,とくに脊椎の転移において,椎体症候群と呼ばれる特徴的な関連痛が発生する。頸椎の転移では後頭部や肩甲背部に,腰椎の転移では腸骨や仙腸関節に,仙骨の転移では大腿後面に痛みがみられる。機序は明らかになっていない。
❶ 体性痛
[定 義] 皮膚や骨,関節,筋肉,結合組織といった体性組織への切る,刺すなどの機械的刺激が原因で発生する痛み。
[痛みの特徴] 骨転移の痛み,術後早期の創部痛,筋膜や筋骨格の炎症や攣縮に伴う痛みなどが挙げられる。組織への損傷あるいは損傷の可能性が原因で発生し,ほとんどの人が急性あるいは慢性に経験する痛みである。損傷部位に痛みが限局しており,圧痛を伴う。一定の強さに加えて,時に拍動性の痛みやうずくような痛みが起こる。さらに体動に随伴して痛みが増強する。骨・関節などの深部体性組織に病巣がある場合は,病巣から離れた部位に痛みを認めることがある(注,関連痛参照)。
[痛みの機序](図1) 体性痛はAδ線維,C 線維の2 種類の末梢感覚神経(一次ニューロン)で脊髄に伝えられる。伝導速度の速いAδ線維は鋭い針で刺すような局在の明瞭な痛みを,伝導速度が遅いC 線維は局在の不明瞭な鈍い痛みを伝える。これらの神経の自由終末に侵害受容器が存在するが,がんが増殖すると,がん自体あるいはがんによって局所に誘導された免疫細胞,破壊された組織から侵害受容器を刺激する化学物質が放出される。また,増大したがんが直接に侵害受容器を刺激するようになる。一次ニューロンは脊髄後角から脊髄に入り,主に脊髄視床路ニューロン(二次ニューロン)とシナプスを形成する。興奮した一次ニューロンからグルタミン酸などの興奮性アミノ酸が放出され,二次ニューロン細胞膜上の受容体に結合することで痛みの情報が伝達される。この刺激が視床から大脳知覚領野に伝えられることで痛みと認識される。
[治療薬の選択] 通常,非オピオイド鎮痛薬・オピオイドが有効であるが,体動時の痛みの増強に対してはレスキュー薬の使用が重要である。また,骨転移痛に対するビスホスホネート,デノスマブなどのbone-modifying agents(BMA)や筋攣縮に対する筋弛緩作用のある薬剤など,病態に基づく鎮痛補助薬の併用が必要な場合がある(Ⅱ-4-3 鎮痛補助薬の項参照)。
❷ 内臓痛
[定 義] 食道,胃,小腸,大腸などの管腔臓器の炎症や閉塞,肝臓や腎臓,膵臓などの炎症や腫瘍による圧迫,臓器被膜の急激な伸展が原因で発生する痛み。
[痛みの特徴] 胸部・腹部内臓へのがんの浸潤,圧迫が原因で発生する。内臓は体性組織と異なり,切る,刺すなどの刺激では痛みを起こさない。固形臓器(肝や腎など)の場合は被膜の急激な伸展,管腔臓器の場合は消化管内圧の上昇を起こすような圧迫や伸展,内腔狭窄が原因で痛みが発生する。「深く絞られるような」あるいは「押されるような」などと表現される痛みで,局在が不明瞭である。悪心・嘔吐,発汗などの随伴症状を認める場合がある。肝臓がんで肩が痛くなるなど,病巣から離れた部位に痛みが発生することがある(注,関連痛参照)。
[痛みの機序](図1) 内臓の痛みもAδ線維,C 線維といった末梢神経で脊髄に伝えられるが,体性組織よりも線維の数が少なく,C 線維の割合が多いという特徴をもつ。また,複数の脊髄レベルに分散して入力されることから,痛みが広い範囲に漠然と感じられるものと考えられる。その一方で内臓周囲に炎症が発生すると,神経の興奮閾値が低下してより興奮しやすくなる,いわゆる感作が発生する。また,生理的状態では機能していないC 線維(silent nociceptor)が活性化され,痛みを伝えるようになる。こうした状況下では痛みの程度も非常に強くなり,関連痛と呼ばれる病巣から離れた部位に痛みが発生する原因にもなると考えられる。
[治療薬の選択] 非オピオイド鎮痛薬・オピオイドが有効である。
図1 がん疼痛の種類と痛みの伝達
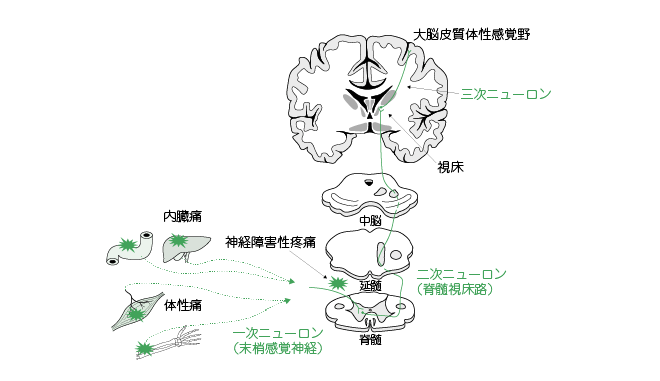
❸ 神経障害性疼痛
[定 義] 痛覚を伝える神経の直接的な損傷やこれらの神経の疾患に起因する痛み。
<解 説>
国際疼痛学会は1994 年に「末梢,中枢神経系の直接の損傷や機能障害や一過性の変化によって始まる,または起こる痛み」と定義した。しかし「機能障害」という言葉は,炎症性疼痛の二次性の神経可塑性変化や神経疾患の経過中の間接的原因で発生する筋・骨格由来の痛みも含めてしまう可能性があることから,直接的な神経損傷を伴うことを前提としたいくつかの再定義を経て2011 年に新しい定義が採用された。本ガイドラインでもこの定義を用いることとする。
[痛みの特徴] 障害された神経の支配領域にさまざまな痛みや感覚異常が発生する。通常,疼痛領域の感覚は低下しており,しばしば運動障害や自律神経系の異常(発汗異常,皮膚色調の変化)を伴う。
(1)刺激に依存しない自発痛
「灼けるような」持続痛(灼熱痛*1)や,「槍で突きぬかれるような」,「ビーンと走るような」電撃痛*2が混じることが多い。
(2)刺激に誘発される痛み
痛み刺激を通常より強く感じる痛覚過敏*3や,通常では痛みを起こさない刺激によって引き起こされる痛みであるアロディニア*4が特徴的である。
(3)異常感覚
自発的,または,誘発的に生じる痛みではない異常な感覚がみられる。不快を伴わない場合(異常感覚【不快を伴わない】,paresthesia)と,不快を伴う場合(異常感覚【不快を伴う】,dysesthesia)とがある。なお,用語の定義は日本ペインクリニック学会編集「ペインクリニック用語集」(第3 版)に準じた。
*1:灼熱痛
「灼けるような」痛みを指し,burning pain と表現されることが多い。この他にも類似の表現が複数あるが,本ガイドラインでは,「灼けるような」(burning)を主に用いた。
*2:電撃痛
発作的に生じる,「槍で突きぬかれるような」(lancinating pain),「ビーンと走るような」(shooting pain)痛み。この他にも類似の表現が複数あるが,本ガイドラインでは,「槍で突きぬかれるような」(lancinating),「ビーンと走るような」(shooting)を主に用いた。
*3:痛覚過敏(hyperalgesia)
痛覚に対する感受性が亢進した状態。通常では痛みを感じない程度の痛みの刺激に対して痛みを感じること。
(参考)痛覚鈍麻(hypoalgesia)
痛覚に対する感受性が低下した状態。通常では痛みを生じる刺激に対して痛みを感じない・感じにくいこと。
*4:アロディニア(allodynia)
通常では痛みを起こさない刺激(「触る」など)によって引き起こされる痛み。異痛(症)と訳される場合があるが,本ガイドラインでは,アロディニアと表現した。
[痛みの機序](図2) 神経障害に伴う痛みのメカニズムとして主に異所性神経活動,感作,脱抑制の3 つが関与すると考えられている。
図2 神経障害性疼痛と中枢性感作の発生機序
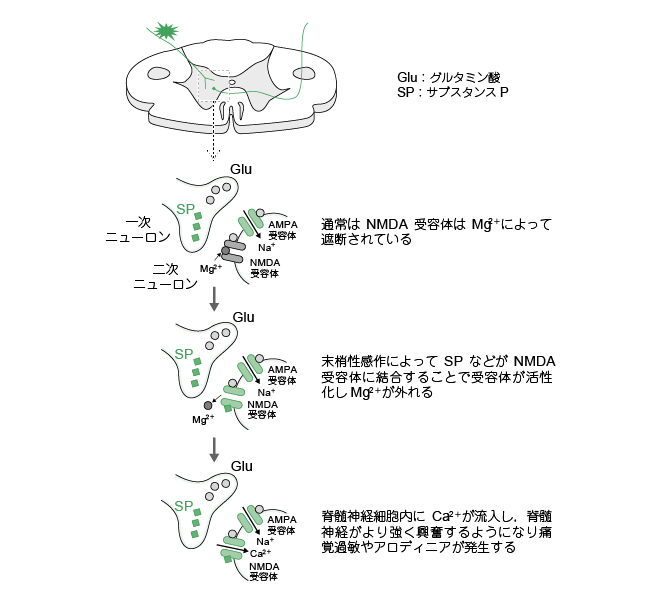
- 異所性神経活動:末梢の感覚神経が損傷を受けると,神経線維や後根神経節上に電位依存性Na+チャネルが発現し,自然発火を繰り返すことにより痛み刺激がなくても持続的な痛みや発作性の痛みを発生させると考えられている。
- 感作:痛み刺激が持続すると神経の刺激閾値が低下し,軽微な刺激でも痛みを伝えるようになる(末梢性感作)。末梢神経の感作に伴って,中枢側末端にあるCa2+チャネルが開口し,Ca2+が神経細胞内に流入すると,グルタミン酸やサブスタンスP などが放出され,N-methyl-D-aspartate(NMDA)受容体の活性化が起こると,中枢神経系の感作も発生し,より強い痛みが,広い範囲に発生するようになる(中枢性感作)。
- 脱抑制:痛みの伝達系のなかには,脳幹から脊髄後角に投射して痛みの伝達を抑制する神経系があり,痛みによって放出されるノルアドレナリンやセロトニンによって活性化されているが,強い痛みが持続すると機能低下を起こす。また,神経障害に伴って脊髄後角のγ-aminobutyric acid(GABA)作動性抑制性介在ニューロンが消失することもわかっており,抑制系が機能低下することも神経障害性疼痛のメカニズムの一つである。
[診 断] 神経障害性疼痛の診断は,国際疼痛学会などの特別委員会で作成されたアルゴリズムを用いて行う(図3)。すなわち,①痛みの範囲が神経解剖学的に妥当,かつ②体性感覚系の損傷や神経疾患を疑う症状を伴っており,③感覚異常などの神経学的所見や神経損傷を示唆する画像所見などの客観的なデータがある場合に,神経障害性疼痛と診断する。
図3 神経障害性疼痛の診断アルゴリズム(国際疼痛学会)
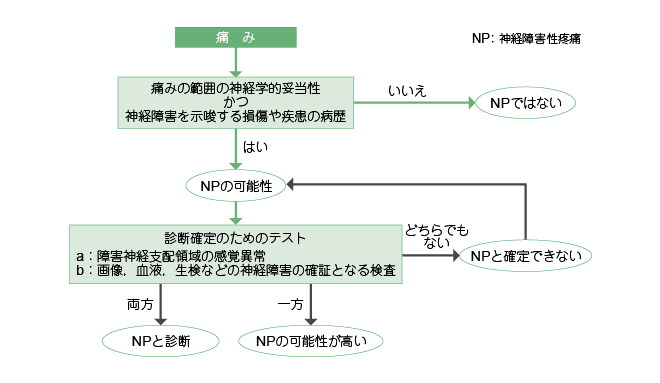
〔Treede RD, et al. Neurology 2008;70:1630-5 より改変〕
[治療薬の選択] 非オピオイド鎮痛薬・オピオイドの効果が乏しいことがあるため,鎮痛補助薬*の併用を考慮する(Ⅱ-4-3 鎮痛補助薬の項参照)。
*鎮痛補助薬
主たる薬理作用には鎮痛作用を有しないが,鎮痛薬と併用することにより鎮痛効果を高め,特定の状況下で鎮痛効果を示す薬物(抗うつ薬,抗けいれん薬,NMDA 受容体拮抗薬など)。非オピオイド鎮痛薬やオピオイドだけでは痛みを軽減できない場合に選択される。参照。
【参考文献】
1) Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, et al. Neuropathic pain:redefinition and a grading system for clinical and research purposes. Neurology 2008;70:1630-5
2) Bruera E, Higginson IJ, Ripamonti C, et al eds. Textbook of Palliative Medicine, Hodder Arnold, 2006
3) Jensen TS, Baron R, Haanpää M, et al. Commentary:A new definition of neuropathic pain. Pain 2011;152:2204-5
4) 日本ペインクリニック学会用語委員会 編.ペインクリニック用語集,第3 版,東京,真興交易医書出版部,2010
2.痛みのパターンによる分類
痛みは1 日の大半を占める持続痛と,突出痛(breakthrough pain)と呼ばれる一過性の痛みの増強の組み合わせで構成される(図4)。
図4 痛みのパターン・患者からみた痛み
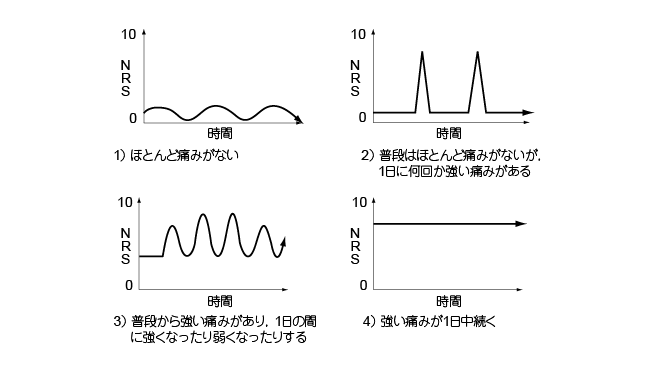
❶ 持続痛
[定 義] 「24 時間のうち12 時間以上経験される平均的な痛み」として患者によって表現される痛み。
[特 徴] 鎮痛薬により緩和されている持続痛と,鎮痛薬が不十分あるいは痛みの急速な増強のために緩和されていない持続痛がある。治療やがんの進行に伴い持続痛の程度も変化するため定期的な評価が必要である。
❷ 突出痛(breakthrough pain)
[定 義] 持続痛の有無や程度,鎮痛薬治療の有無にかかわらず発生する一過性の痛みの増強。
<解 説>
突出痛には統一した定義がない。本ガイドラインにおいては,持続痛に対する痛みのパターンを表す言葉として定義を行った。一方,Oxford Textbook of Palliative Medicine(第4 版)を含む最近の欧米の教科書や研究においては「オピオイド投与により持続痛のコントロールされている患者に発生する一過性の痛みの増強」という定義を用いているものが多い。一過性に発生し,自然に終息する性質の痛みを定義したものであることから,この定義には本邦の定義に含まれる定時鎮痛薬の切れ目の痛みは含まれないことになる。欧米にはすでに,この定義の突出痛治療薬として,効果発現が速く,効果持続時間が短い製剤が存在していることが背景にあると考えられる。治療アプローチとしてはどちらの定義であっても,持続痛を緩和したあとに残存する突出痛を治療介入の必要な突出痛として対処することに変わりはないので,本ガイドラインにおいては痛みのパターンを表す言葉として定義することとした。
[特 徴] 痛みの発生からピークに達するまでの時間は3 分程度と短く,平均持続時間は15〜30 分で,90%は1 時間以内に終息する。痛みの発生部位は約8 割が持続痛と同じ場所であり,持続痛の一過性増強と考えられている。
[サブタイプと治療アプローチ] 突出痛は,発症が急速で持続が短いという一般的な特徴がある。いくつかのサブタイプに分類することが提案されているが国際的に定まった分類はない。本ガイドラインでは,治療に反映することができるという点から,「予測できる突出痛」,「予測できない突出痛」,「定時鎮痛薬の切れ目の痛み」の3 つに分類する。特徴にあわせた治療を行うことが重要である(表2)。
| 体性痛 | 内臓痛 | 神経障害性疼痛 | |
|---|---|---|---|
1 予測できる突出痛※ |
歩行,立位,坐位 保持などに伴う 痛み(体動時痛) |
排尿,排便, 嚥下などに 伴う痛み |
姿勢の変化による神経圧迫, アロディニアなどの刺激に 伴う痛み |
2 予測できない突出痛 |
|||
1)痛みの誘因があるもの※ |
ミオクローヌス, 咳など不随意な 動きに伴う痛み |
消化管や膀胱 の攣縮などに 伴う痛み (疝痛*1など) |
咳,くしゃみなどに伴う痛み (脳脊髄圧の上昇や,不随意な 動きによる神経の圧迫が誘因と なって生じる) |
2)痛みの誘因がないもの |
特定できる誘因がなく生じる突出痛 | ||
3 定時鎮痛薬の切れ目の痛み |
定時鎮痛薬の血中濃度の低下によって,定時鎮痛薬の投与前に 出現する痛み |
||
※:痛みの誘因のある,「予測できる突出痛」と,「予測できない突出痛」のうち「痛みの誘因があるもの」 をあわせて,「随伴痛」*2と呼ぶことがある。
*1:疝痛(colicky pain)
消化管の攣縮に伴う痛み。ぜん動痛と呼ばれることがある。
*2:随伴痛(incident pain)・体動時痛(pain with movement,movement-related pain)
一般的に,「incident pain」とは「特定の動作や兆候に伴って生じる痛み」を指し,動作に伴って生じる痛み(体動時痛,動作痛;pain with movement,movement-related pain)としばしば区別せずに用いられてきた。しかし,「特定の動きや兆候」には,歩行や立位など随意的な動作ばかりではなく,随意的ではないミオクローヌスや咳,内臓の攣縮も含まれうるため混同が生じている。
本ガイドラインでは,暫定的に, 随伴痛(incident pain)を「特定の動作や兆候に伴って生じる痛み」,体動時痛を「意図的な体動に伴って生じる痛み」と定義する。すなわち,随伴痛とは,何らかの動作や兆候に伴って生じる痛みすべて含む概念とし,体動時痛は随伴痛の一部とした。「随伴痛」という言葉は混同されやすいため,ガイドライン本文では記載を避けた。
(1)予測できる突出痛(predictable breakthrough pain)
予測可能な刺激に伴って生じる突出痛。意図的な体動に伴って生じる痛み(体動時痛)が代表的である。突出痛の誘因となる行為を予防して避けることが重要である。誘因が避けられない場合には,経口投与では30〜60 分前に,皮下投与では15〜30 分前に,静脈内投与では直前にレスキュー薬を予防投与するなどの対処を行う。フェンタニル口腔粘膜吸収剤の予防投与について一定の見解はないが,血行動態から10〜30 分前を目安にした予防投与を検討する。
(2)予測できない突出痛(unpredictable breakthrough pain)
痛みの出現を予測できない突出痛。痛みの誘因があるがいつ生じるかを予測することができない場合と,痛みを引き起こす誘因そのものがない場合とがある。
①痛みの誘因があるもの
ミオクローヌス,咳,消化管や膀胱の攣縮など,意図的ではない体の動きに伴って生じる突出痛。誘因は同定できても出現を予測することができない。迅速なレスキュー薬対応に加えて,痛みの誘因の頻度を減少させるような病態へのアプローチを行う。
②痛みの誘因がないもの(誘因のない突出痛,spontaneous pain*3)
痛みの誘因がない突出痛。持続がやや長く,しばしば30 分を超えるものがある。痛みの特徴に応じてレスキュー薬が迅速に使用できるような対応を行う。さらに,神経障害性疼痛に伴う発作痛はレスキュー薬のみでは対応が困難な場合が多いので,効果的で副作用の少ない鎮痛補助薬を選択する必要がある。
*3:誘因のない突出痛(spontaneous pain)
spontaneous pain とは,特定できる誘因がなく生じる突出痛を指す言葉であり,idiopathic pain と呼ばれることもある。本ガイドラインでは,「誘因のない突出痛」と訳した。
(3)定時鎮痛薬の切れ目の痛み(end-of-dose failure)
定時鎮痛薬の血中濃度の低下によって,定時鎮痛薬の投与前に出現する痛み。発現が緩徐で持続が最も長い。定時鎮痛薬の増量や,投与間隔の変更を考慮する。
(冨安志郎)
【参考文献】
1) Payne R. Recognition and diagnosis of breakthrough pain. Pain Med 2007;8:S3-7
2) McCarberg BH. The treatment of breakthrough pain. Pain Med 2007;8:S8-13
3.痛みの臨床的症候群
がん患者にみられる痛みは,①がんによる痛み,②がん治療による痛み,③がん・がん治療と直接関連のない痛みに分類される(表3)。「がんによる痛み」とは,がん自体が原因となって生じる痛みであり,神経学的に内臓痛(膵臓がんの痛みなど),体性痛(骨転移痛など),神経障害性疼痛(腫瘍の浸潤によって生じる脊髄圧迫症候群や腕神経叢浸潤症候群など)に分類される。「がん治療による痛み」とは,外科治療,化学療法,放射線治療など,がんに対する治療が原因となって生じる痛みであり,術後痛症候群,化学療法後神経障害性疼痛,放射線照射後疼痛症候群などがある。「がん・がん治療と直接関連のない痛み」とは,上記のいずれにも該当しない原因の痛みであり,もともと患者が有していた疾患による痛み(脊柱管狭窄症など),新しく合併した疾患による痛み(帯状疱疹など),あるいは,がんにより二次的に生じた痛み(廃用症候群による筋肉痛など)を含む。
本ガイドラインでは,上記の「がんによる痛み」をがん疼痛とよび,本ガイドラインの対象となる痛みを指すこととする。
また,がん患者が痛みを生じた場合には,腫瘍学的に緊急的対処を必要とする「オンコロジーエマージェンシーに関係した痛み*1」の場合があるため,オンコロジーエマージェンシーの診断は臨床的に重要である。
1 がんによる痛み |
内臓痛 脊髄圧迫症候群 |
|---|---|
2 がん治療による痛み |
術後痛症候群 開胸術後疼痛症候群 化学療法誘発末梢神経障害性疼痛 |
3 がん・がん治療と直接関連のない痛み |
もともと患者が有していた疾患による痛み(脊柱管狭窄症など) 新しく合併した疾患による痛み(帯状疱疹など) |
〔日本臨床腫瘍学会 編.新臨床腫瘍学,第2 版,南江堂,2009,NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology,Adult cancer pain〕
*1:オンコロジーエマージェンシーに関係した痛み
- 脊髄圧迫症候群,硬膜外転移
- 体重支持骨の骨折または切迫骨折
- 脳転移,軟髄膜転移
- 感染症に関係した痛み
- 消化管の閉塞・穿孔・出血
❶ がんによる痛みの症候群
1 )脊髄圧迫症候群
腫瘍の脊椎転移や浸潤,腫瘍自体が脊髄を圧迫することによって生じる痛みである。肺がん,乳がん,前立腺がんなどに多い。
[特 徴]
- 椎体に転移した腫瘍の後方への広がりに伴って発生することが多いが,椎弓に転移した腫瘍の前方への広がりによる場合もある。
- ほとんどの患者で腰背部痛が先行し,その後,神経刺激・圧迫に伴う感覚・運動障害,膀胱・直腸障害などが増強する。
- 腰背部痛は椎体破壊が原因の鈍痛で,体動や咳などによって増強する。
- 頸胸椎の破壊に伴って肩甲背部・肩に,第12 胸椎〜第1 腰椎破壊に伴って仙腸骨部・腸骨稜に関連痛*2 がみられることがある。
- 放散痛は圧迫・障害された神経根によるもので,頸椎・腰仙椎レベルでは片側性に,胸椎レベルでは両側性(胸腹部の締め付け感として経験される)にみられることが多い。
- 運動障害:神経根障害(radiculopathy)の場合は障害された脊髄分節のみに,脊髄障害(myelopathy)の場合は障害脊髄レベル以下に運動障害を生じる。筋力低下は外科治療,放射線治療,化学療法などにより腫瘍の圧迫を除去しなければ,短期間に対麻痺に移行する。
- 感覚障害:正常領域に比較し触るなどの感覚の低下や過敏,痛み感覚の低下や過敏,痛みではないが不快な感覚異常などが障害神経の支配領域を中心にみられる。
- 膀胱直腸障害:一般に脊髄圧迫の遅い時期に生じる。脊髄円錐・馬尾レベルの障害では早期に生じる。
*2:関連痛
病巣の周囲や病巣から離れた場所に発生する痛みを関連痛と呼ぶ。内臓のがんにおいても病巣から離れた部位に関連痛が発生する。内臓が痛み刺激を入力する脊髄レベルに同様に痛み刺激を入力する皮膚の痛覚過敏,同じ脊髄レベルに遠心路核をもつ筋肉の収縮に伴う圧痛,交感神経の興奮に伴う皮膚血流の低下や立毛筋の収縮を認める。上腹部内臓のがんで肩や背中が痛くなること,腎・尿路の異常で鼠径部が痛くなること,骨盤内の腫瘍に伴って腰痛や会陰部の痛みが出現することなどが挙げられる。
(参考)椎体症候群
骨転移,とくに脊椎の転移において,椎体症候群と呼ばれる特徴的な関連痛が発生する。頸椎の転移では後頭部や肩甲背部に,腰椎の転移では腸骨や仙腸関節に,仙骨の転移では大腿後面に痛みがみられる。機序は明らかになっていない。
[治 療]
- 脊髄圧迫症候群が疑われる場合には緊急MRI 検査を行い,責任病巣を同定する。
- 神経障害の進行を回避するために,放射線治療や外科治療の適応に関して放射線科医や整形外科医に相談する。
- 痛みに対して非オピオイド鎮痛薬・オピオイドに加えて,神経障害性疼痛の合併が考えられる場合は鎮痛補助薬の併用を検討する。神経症状の主体が脊髄圧迫の場合はコルチコステロイドの投与を考慮する。
2 )腕神経叢浸潤症候群
肺尖部腫瘍が腕神経叢に浸潤することによって生じることが多い。リンパ腫,肺がん,乳がんに多い。
[特 徴] 痛みは高頻度に認められ,神経学的異常に先行する。疼痛部位は肘,前腕中央,第4 指,第5 指であることが多く,後に第7 頸椎〜第1 胸椎神経根領域のしびれ感や筋力低下が進行する。
- 下位腕神経叢浸潤に由来した症状が多く,第5,6 頸椎神経根などの上位神経叢に由来する症状はまれである。上位神経叢に由来する症状として上肢帯や指先,第1 指や第2 指に痛みがみられることもあるが,多くの鎖骨上・腋窩部の転移性病変では神経学的異常を伴わない。
- ホルネル症候群*1 は傍脊椎部への浸潤を示唆する。
[治 療] 「Ⅲ-4-1 神経障害性疼痛」に準ずる(参照)。
*1:ホルネル(Horner)症候群
仰臥位で片脚を伸展させたまま他動的に挙上するテスト。挙上角度が70 度以下なら陽性。下部腰仙部神経叢障害による筋力低下・痛みで歩行などが困難となる。
3 )腰仙部神経叢浸潤症候群・悪性腸腰筋症候群
骨盤内腫瘍の腰仙部神経叢への浸潤によって両下肢の筋力低下・痛みが生じ,体動困難となる。下肢痛,下肢筋力低下,下肢浮腫,直腸腫瘤,水腎症などを合併することがある。大腸がん,婦人科がんなどに多い。
[特 徴] 本症候群の多くの患者では,骨盤痛と両下肢痛がみられ,続いてしびれ感,感覚障害,筋力低下が進行する。ただし,痛みしかみられず神経学的異常を伴わないこともしばしばある。
- 上部腰仙部神経叢障害は第1〜第4 腰椎への腫瘍浸潤で生じる。大腸がんの直接浸潤によるものが多い。痛みは背部,下腹部,側腹部,腸骨稜,大腿前面〜外側に認められる。
- 下部腰仙部神経叢障害は第4 腰椎〜第1 仙骨への腫瘍浸潤で生じる。直腸がん,婦人科がんなど骨盤内腫瘍による直接浸潤が原因となることが多い。疼痛部位は臀部,会陰部,大腿後面,下腿に認められる。筋力低下,感覚低下などは第5 腰椎,第1 仙骨領域に認められ,アキレス腱反射の減弱,下肢浮腫,膀胱直腸障害,仙骨部圧痛,下肢伸展挙上テスト*2(straight leg raising test)陽性などが認められる。自律神経系の異常として発汗異常,血管拡張などが認められることがある。
- 画像上または病理学的に証明される患側腸腰筋内の悪性疾患の存在により,患側股関節の屈曲位保持(股関節伸展にて疼痛増強),ならびに第1〜第4 腰椎の腰仙部神経叢障害を来すものとして悪性腸腰筋症候群が知られている(Ⅲ-4-6 悪性腸腰筋症候群による痛みの項参照)。
[治 療] 「Ⅲ-4-1 神経障害性疼痛」に準ずる(参照)。
*2:下肢伸展挙上テスト
仰臥位で片脚を伸展させたまま他動的に挙上するテスト。挙上角度が70 度以下なら陽性。下部腰仙部神経叢障害による筋力低下・痛みで歩行などが困難となる。
❷ がん治療による痛みの症候群
1 )開胸術後疼痛症候群
開胸手術後に発生する痛みで,その特徴によりおおまかに3 つの群に分けられる。
[特 徴]
- 2 カ月程度で徐々に軽減,消失する痛みで,最も発生頻度が高い。開胸手術操作(肋骨の牽引,切除)に伴う筋層破壊や肋間神経障害などが原因と考えられる。痛みが再増強する場合は再発を考慮する。
- 術後から持続していた痛みが経過観察中に増強する場合がある。局所再発や感染の発症が主な原因である。
- 最大8 カ月間持続,または徐々に軽減する痛みの場合がある。これは腫瘍の再発とは関連がない。
- いずれにしても8 カ月以上持続する痛みやいったん緩和がみられたあとの痛みの再燃は腫瘍再発や感染を疑う。
[治 療] 痛みの特徴を問診し,必要に応じてMRI やCT などの画像検査,感染徴候の有無などの血液検査を行い,原因に対するアプローチを行う。痛みの種類や程度に応じて鎮痛薬,鎮痛補助薬の投与を行う。
2 )乳房切除後疼痛症候群
局所切除から拡大切除までのさまざまな乳房手術に伴って発生する痛みである。
[特 徴]
- 上腕内側,腋窩や前胸壁部などの「締め付けるような」,「灼けるような」,と表現される異常感覚を伴っていることが多い。疼痛部位の感覚低下を伴うことがある。
- 手術操作による肋間上腕神経(第1〜2 胸椎の皮枝)の神経障害が主な原因と考えられている。
- 腋窩郭清を行わずにセンチネルリンパ節切除を行うことで同症候群を減らすことができるとの報告や,郭清を行わずに放射線治療をすることで同症候群を減らすことができるといった報告がある。
- 術直後〜半年までに発症することが多い。年余を超えて発症するのはまれであるので胸壁などに再発がないか特に注意する。
[治 療] 鎮痛薬が無効の場合は「Ⅲ-4-1 神経障害性疼痛」に準じて鎮痛補助薬を使用する(参照)。
3 )化学療法誘発末梢神経障害に伴う痛み
化学療法による神経障害のうち末梢神経障害に伴って生じるものであり,手袋靴下型に分布する神経障害性疼痛である。
[特 徴]
- 手指・足趾の持続的で灼けるような痛みや電撃痛などが多い。
- パクリタキセルやオキサリプラチン,シスプラチン,ビンカアルカロイド系薬剤などでみられることが多い。
- 感覚低下,筋力低下,腱反射低下,自律神経障害などを伴うことがある。
[治 療] 痛みの心理社会面に及ぼす影響などを注意深く評価し,効果と副作用を評価しつつ「Ⅲ-4-1 神経障害性疼痛」に準じて鎮痛補助薬を使用する(参照)。また,薬物療法以外の痛み治療法の併用を考慮する(Ⅱ-8 参照)。痛みの程度は治療薬の投与前後,時間経過で変化するので,漫然と薬物療法を行わない。
4 )放射線照射後疼痛症候群
放射線治療の晩期障害*(組織の線維化など)により痛みが生じる。
*:放射線治療の晩期障害
放射線治療後,数カ月以上経ってから現れる後遺症。頻度はごくまれだが,発症すると回復は難しい。
[特 徴]
- 照射線量(用いられた放射線の量,1 回量と総量)や治療範囲の広さにより,発現率は異なる。
- 照射後,月〜年単位で発生・徐々に進行する病態である。
- 末梢神経障害,脊髄障害など,発症部位に応じた症状が出現する。
- 腫瘍再発との鑑別が必要である。
[治 療] 痛みの特徴を評価し,鎮痛薬,鎮痛補助薬を投与する。薬物療法以外の痛み治療法の併用を考慮する(Ⅱ-8 参照)。
(北條美能留,冨安志郎)
<2.痛みの包括的評価>に続く